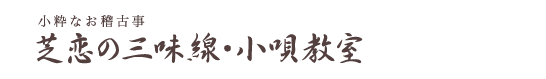小唄「ままならぬ」のご紹介。
ホーム
> 小唄「ままならぬ」のご紹介。
小唄「ままならぬ」のご紹介。
2025年05月06日(火)12:53 PM
「ままならぬ」
まならぬ浮世と知れど逢いたさに
用ありげなる玉章は
こころ赤間の小硯に
受けてほしさよ萩の露。
幕末の江戸端唄から出た江戸小唄で
ある。
「赤間」は赤間石のことで、山口県
厚狭郡原西村平沼田に産し、その赤
褐色の濃いものは硯石として有名で
ある。
唄は、赤間石の産する長州の勤王の
志士の一人が、故郷に残した一人の
女性を想うてその感懐をもらしたも
のであろう。
長州萩には、松下村塾があり、若者
は何れも対幕のため京に出たり、薩
長に走ったり、東奔西走して多忙の
身であったというのが「ままならぬ
浮世」である。その多忙の中から、
故郷に残した許嫁に玉章《文》を
書いて送る。
この愛情を、どうぞむねの「小硯」
にしっかりと受けとめておいてほし
いという所で、「こころ赤間」は燃
えるような赤心と赤間硯とをかけた
ものである。
「萩の露」の萩は、長州の地名の一
つで、長州に住むいとしい人という
意味であろう。
素朴な江戸小唄であるが、暖い人の
心がしみじみと通う小唄である。
この原唄の江戸端唄は、安政年間ま
での唄本に見えぬので、多分万延以
降に作られたものであろう。
「江戸小唄」 木村菊太郎著より引用
この小唄はゆったり、静かな心持ち
で唄うとしみじみとした想いが伝わ
ると思います。