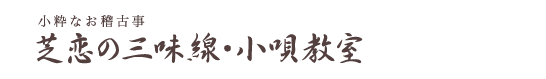小唄「朝顔の」ご紹介。
「朝顔の」
作詞 木村富子
作曲 十二世片岡仁左衛門
朝顔の 明日待つ間や垣根越し
闇を流るる蛍光に 初の御見をしみじ
みと 胸にやきつく面影も 逢わでこ
の夜を宇治川の 霧が濡らした瑠璃の
色。
芝居小唄『増補 生写朝顔日記』時代物。
京都岡崎聖護院の町外れに閑居する、も
と芸州岩戸の家老秋月弓之助の一人娘深
雪は、四月の末乳母と宇治の蛍狩にゆき、
九州大内家の家臣で儒学修業に京へ来て
いる宮城野阿曾次郎と呼ぶ美しい侍と互
いに見染め合うが、その時阿曾次郎は金
地に花を描く扇に、『露の干ぬ間の朝顔
を、照らす日影のつれなさに、あわれ一
村雨のはらはらと降れかし。』という歌
を書いて与える。
それから三ヶ月、朝顔の咲く頃、深雪の
父は国元に一揆が起こったとの書状によ
り急いで帰国することとなり、深雪は明
石の浦で阿曾次郎と果敢ない別れをする
。
深雪はそれ以来阿曾次郎を慕い、大内家
の駒沢治郎左衛門との縁談が起こったの
を、駒沢こそは阿曾次郎が帰国して叔父
駒沢了庵の養子として家督を継いだため
の改名と知らぬ深雪は、阿曾次郎への操
を立てて家出し、流浪する間に盲目とな
り、阿曾次郎をたづねて各地をさまよう
。
一年経った晩秋の夜、東海道島田の宿の
戎屋で、客の所望により『露の干ぬ間に
』の唱歌を、琴に合わせて唄うが、この
客こそ駒沢で、駒沢は国元へ帰る途中の
ため、わざと名乗らず、朝顔の唄と本名
を記した扇に眼病の霊薬を添えて亭主に
渡して出立する。
それと知った深雪は、狂気のごとく駒沢
のあとを追うが、大井川は夜来の雨で増
水のため川止めとなる。
悲嘆の極、川へ身をおどらせようとした
深雪は、忠僕関助に止められ、宿屋の亭
主徳右衛門(旧臣)の身を殺しての情けで
たちまち眼病は平癒し、関助の供で首尾
よく駒沢の家をたづねて婚儀を取り結び
、一方駒沢の忠義で岩代の奸計があらわ
れ、大内の家は安泰となる。
小唄は、盲目となった深雪が、一年前の
四月の蛍狩の夜、阿曾次郎との初の御見
をしみじみと思い浮かべる所を唄ったも
ので、女性の作になるこの歌詞は、女心
の切なさ悲しさを描いて、近代的感覚を
表現し、作曲はまた朝顔役者の仁左衛門
の手になる得難い小唄の一つである。
冒頭の『朝顔の明日待つ間や垣根ごし』
は、朝顔の花が四ツ目垣にからまって明
日の朝の朝露の恵みを受けて咲くのを待
っているように、深雪が阿曾次郎と逢え
る日を待ち焦がれているという意味で、
『闇を流るる蛍火に』以下は深雪の宇治
の蛍狩の想い出を唄ったものである。
「芝居小唄」木村菊太郎著より引用
芝居小唄をお稽古する際にはそのお芝居
を知らないと歌詞の理解が出来ず、詰ま
りませんね。
この短い歌詞にこれだけのストーリーが
あって、それをわかってこそ唄う心情も
味わい深いものになるのでしょう。
« 小鼓のお稽古 | しちふく寄席 三遊亭ごはんつぶ »